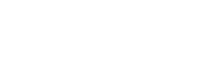転職後にも効果を発揮「アンガーマネジメント」
アンガーマネジメントとは?
アンガーマネジメントとは、怒りを覚えるシーンや対象についての自己理解を深め、イライラや怒りの感情をうまくコントロールし、そのエネルギーを他の事に使うようにすることなどをいいます。大事なのは、怒りの感情が起こったときに、どのような対処をするかです。
アンガーマネジメント=「怒らない」 ということではない
アンガーマネジメントでよく間違われやすいのが、アンガーマネジメント=怒らないという考えです。自分の怒りの感情をコントロールすることで結果として怒りをおさえるのですが、怒らなかったからアンガーマネジメントできたのかというと一概にそうとは言い切れません。
アンガーマネジメントの基本的な考えにもなりますが、怒った結果後悔しないかどうか、という考えのもと、怒ったほうがいいという考えなら怒るべきだといわれています。
またアンガーには怒りだけではなく、イライラする感情も含まれているため、怒りの感情やイライラの感情をうまくコントロールするためのトレーニングと考えるのがいいでしょう。
今アンガーマネジメントが必要とされる理由
今アンガーマネジメントが必要とされるのはなぜなのでしょうか?
怒りの感情は、人と何かの接触を持ったときに多く起こります。怒ることが問題になることが多い場所として、職場があげられます。
よくあるケースとして上司が部下に対して怒るというものです。ありがちなシーンですが、現在では部下や同僚に対して怒るということでハラスメントになり、感情に任せて怒鳴るといったことが問題になっています。
若い世代は怒られることで萎縮してしまう、なぜ自分だけ怒られるのかと不満の感情が発生する、自分の意見が通らないというようにモチベーションが低下してしまい、そのまま退職になるケースも少なくありません。そこで、怒りの感情をコントロールするアンガーマネジメントが必要とされているのです。
怒ることによるデメリットは?
そもそも怒ることには、デメリットが多くあります。
体調面の変化
体調面でのデメリットがあげられます。怒りを感じると心拍数があがり、血圧が急激に上がるなど体の変化が起こります。場合によっては、心臓発作のリスクも出てくるので注意しなければなりません。
人間関係の悪化
人間関係にもよくない影響を与えます。怒りの感情をぶつけられていい気持ちがする人はいません。怒ることで相手との関係悪化につながり、関係修復のためには多大な労力・時間を要することになります。
周囲のモチベーション低下
自分が怒ったことで気まずい雰囲気になり、周りの人のモチベーションの低下にもつながります。やる気を失わせて目標達成できなかったとなれば、自分の評価の低下にもつながるかもしれません。
自分の職場イメージ低下
立場を利用しての嫌がらせやいじめと取られれば、ハラスメントにもつながる可能性もあります。あの人はすぐ怒る人だから気軽に相談できない、といったイメージがつくと思い通りのマネジメントができず、パフォーマンスが悪化、そしてまた怒る、イメージがさらに悪化する、といった悪循環に陥ってしまう可能性があります。
判断力の低下
怒って興奮した状態では、判断力が鈍っているので、正しい判断を下すことができなくなります。ビジネスシーンでは、決断を迫られることが次々に起こるので、怒りをいつまでも引きずっていると判断することが難しくなります。間違った判断やいい加減な判断をして、大きなトラブルを引き起こしてしまうかもしれません。
アンガーマネジメントのメリットとは
アンガーマネジメントを実践すると、さまざまなメリットが期待できます。
健康な状態の維持
身体的には、体への負担が減って健康な状態を維持できます。イライラしたり、カッカと怒ることがなくなるので、血圧が安定するでしょう。
自分の精神安定により部下のモチベーション向上
精神的にも大きなメリットがあります。これまで感情に任せて怒っていたのが、相手にあたるのではなく、自分のモチベーションに変えられるようになります。自分の先入観だけで判断をしなくなり、相手の意見を受け入れることができるようになるので、視野が広がっていくでしょう。部下の言うことを一方的に否定して怒ることがなくなるので、部下も意見を言いやすくなり、モチベーション高く仕事をしてくれるかもしれません。
部下や周囲との良好な関係
部下や周囲との良好な関係を構築できるようになるのも利点です。怒りではなく、相手に納得してもらおうと努力するようになるので、相手も心を開いて話に耳を傾けてくれるでしょう。アンガーマネジメントによって、コミュニケーション能力もアップするというわけです。
また、一方が怒ると相手にも怒りの感情がわきやすくなり、怒りの連鎖が発生することが多くあります。怒りに怒りで対応しても、嫌な感情が残るだけで、何もいいことがありません。アンガーマネジメントを身につければ、このような不毛な争いを避けることも可能になります。
アンガーマネジメントは、怒りの感情と上手に付き合うための一つの技術です。アンガーマネジメントを身につけると、必要のない怒りにふりまわされないで済むようになります。心身に影響の大きい怒りの感情をコントロールできるようになれば、毎日を健康的に過ごすことができるようになるでしょう。
アンガーマネジメントの方法
アンガーマネジメントは具体的にどのように実践すればよいのでしょうか。アンガーマネジメントでは、衝動や思考をコントロールすることで、怒りの感情を鎮めていくことができるというふうに考えます。では、衝動や思考をどのようにしてマネジメントしていけばよいのでしょうか。
衝動 - 怒りを感じたら6秒間我慢
まず、「衝動」のコントロールです。誰でも、怒りが涌き起こってくる体験をしたことがあると思います。怒りは、何かを引き金にして高まる感情で、うまくコントロールできないと、そのまま怒りがどんどん大きくなって爆発してしまうことがあります。
怒りを感じてからのピークは6秒で、この6秒間にどのようなことをするのかで、怒りを爆発させるか鎮められるかが決まるといわれています。怒ると衝動的にものにあたったり、人にあたったりするのも、この6秒間の怒りの衝動を原因とするものです。ですから、アンガーマネジメントを行うには、衝動の6秒をぐっと我慢する、やり過ごすということが大切になります。
6秒間我慢するための方法
怒りを感じたとき、一番いけないのは腹が立つ状況にいつまでもいることです。
目の前に怒りの種がある状況にいれば、いつまで経っても怒りがおさまるわけがありません。いつまでもイライラするだけでなく、怒りがどんどんエスカレートする原因にもなります。
1. その場から離れる
怒りの6秒間を耐えるには、意識的に怒りの衝動を抑えられるような行動を取ることが効果的です。腹が立ったら、まずその場から離れるのがよいでしょう。怒っているときは一つの志向にこだわりやすくなっているので、その場から離れて思考をリセットすることが大切です。オフィス内で腹が立つことがあったら、オフィスからいったん出ましょう。建物から出てまったく違う場所に移動しても構いません。外の空気にあたることで気持ちが切り替わることも大いにありえます。
そんなことをしている時間がないと考える方もいると思います。ただ怒りの感情をそのままに仕事をしても効率的なパフォーマンスは出すことができません。それならば一度時間をとり、怒りを抑えてから気持ちを新たに仕事をしたほうがパフォーマンスを上げることができるでしょう。
2. 深呼吸して気持ちを落ち着かせる
場所を移動したら、深呼吸します。興奮していると呼吸が浅くなりがちなので、ゆっくり深呼吸することで気持ちが落ちついていきます。怒っているときは後先が見えなくなっていることも多いので、いったん立ち止まって、怒った後のことを冷静に考えるのも有効です。場所を変えて、思考をリセットすることで怒りの感情が徐々に収まっていきます。屈伸など簡単に体を動かして、気持ちを別のことに向けるのもいいでしょう。
思考 - 相手のことを許容する
自分の考えと違うことをされると怒りの感情が発生する
そもそも怒りの感情が起こるのは、自分が考えていることと違うことを相手にされるからです。たとえば、自分はこういう施策を考えているのに上司や部下が納得してくれない、○○してほしいと思っているのに相手が思うように動いてくれないといった相手への不平・不満が怒りの原因になるのが一般的です。つまり、相手のことを許容できないと思ったときに、怒りが湧いてくるということになります。
ある程度相手の意見は許容する
アンガーマネジメントを行うには、自分がどこまで相手のことを許容できるかを把握することが必要です。我慢して相手のことをすべて受け入れる必要はありません。ただ、自分の意見をすべて押し通したり、相手の意見をすべてダメと否定したりするのではなく、ここまでなら許容できるという境界線を考えることが大事です。
たとえば、職場で部下から○○したいという意見が出たら、そんなものはダメだと一蹴するのではなく、話をよく聞いて、やらせてもいいと思うことは認めてあげましょう。たとえ一部でも意見が認められたら相手は嬉しいものです。こちらの言うことを聞いてもらいたいなら、許容できる範囲で構わないので、相手の意見も認めるようにしましょう。
ビジネスにおいて部下の方が考えるよりも上司の方には様々な事情があり、部下の考えを否定するしかない場合もあるでしょう。すべてを開示して部下に納得してもらう必要はありませんが、しっかりとなぜダメなのかを説明して相手に納得してもらう必要はあるでしょう。
思考 - 割り切る
自分ではどうにもならないことは、怒るのではなく、いさぎよく割り切りましょう。自分の意見が通らなくて腹が立つなら、なぜ通らないのかを考えてみます。その上で、自分ではどうにもならないと判断したら、執着するのではなく仕方がないものとして割り切るようにしましょう。すべてが自分の思い通りにいくわけではありませんから、執着するだけ自分がつらくなります。
(例)転職面接
たとえば、転職面接で面接に落ちてしまったという場面を想定してみましょう。失敗を反省してなぜダメだったのかを考えるのは、次の面接を成功させるためにももちろん大切です。しかし、落ちたという事実のみをずっと引きずってしまうと、落ちたことはもはや変えられない事実なので、怒りや失望の気持ちだけがどんどんふくらんでいってしまいます。
このような場合は、変えられない過去ではなく未来の可能性に目を向けて、前向きの思考をすることが重要です。同じ会社の別のポジションで面接が受けられるかもしれませんし、まったく別の会社の面接を受けたら、すんなり通るかもしれません。もし、面接に何度も落ちてしまったり、ダメな部分がわからない場合も、一人でいらいらせずに割り切って、転職エージェントに何がいけないのか聞いてみるのもひとつの手でしょう。
転職など環境が変わるタイミングはアンガーマネジメントを実践するいい機会
転職後しばらくの間は、新たな職場で自分とは違う価値観に触れることで刺激を得られる一方で、ストレスを感じやすい時期でもあります。
転職だけでなく一つのプロジェクトを複数のメンバーで進める上でも成果を図る評価基準や仕事の進め方は人それぞれ。バックグラウンドや得意・不得意の異なるメンバーが集い、コストやスピードといった様々な重圧の下で協力し合わなくてはなりません。
度重なるストレスから感情に任せて怒ったり、イライラした態度を表に出してしまうと自身の仕事のペースが崩れるだけでなく、ネガティブな空気が蔓延しチームの生産性にも影響しかねません。
管理職こそアンガーマネジメントは有効
最近では日本でも多くの企業が管理職向けトレーニングなどにアンガーマネジメントを採用しています。
上司やプロジェクト・リーダーの場合は感情任せに怒ることを避けて適切に叱る術を会得すれば、自身とチームのストレスを軽減できパフォーマンスを高められると言われています。
感情的に怒ることは部下のモチベーション低下につながりかねない
上司が部下に対して感情的に怒鳴るのを部下はよく見ています。もし自分が部下の立場だったらそれをどう思いますか?少なくともいい気持ちにはならないでしょう。もちろん、怒られてしかるべきタイミングもあるためメリハリは大切ですが、部下が目標に到達できなかった、思い通りの成果が上がらなかったとしたら、自分のマネジメント能力にも関わるため、よく考えてみると自分にも原因があるといえます。
また部下からするとよく怒る上司という悪いイメージがつくため、アンガーマネジメントを使い「よく怒る上司」から「よく指導してくれる上司」となることが必要です。
アンガーマネジメントについては多くの書籍が出ているほか、個人で聴講できる講座も増えています。
テクノロジーの進化でビジネスの速度が上がるなか、転職後のパフォーマンスへの要求は高まっています。
効率的にパフォーマンスを高めるため、または働きやすい職場環境を自ら築くために、リーダーの立場にいる人もそうでない人もアンガーマネジメントに取り組んでみてはいかがでしょうか。
あなたの将来のキャリアをプロに相談しませんか?
ロバート・ウォルターズのキャリアコンサルタントが、これまで多くの方々の転職を成功へ導いてきた実績と経験であなたに最適なキャリアアップと能力発揮のチャンスを提案いたします。
関連コンテンツ
すべて見る海外留学を通じて得られるスキルや経験は、キャリア形成にどのような影響を与えるのでしょうか? 今回は、ロバート・ウォルターズ・ジャパンで海外からの転職を支援しているAyako Shimizu(以下、Shimizu)と、EF(Education First)でセールス・ディレクターを務めるReina Araki(以下、Araki)さんが、海外経験を活かしたキャリア構築について語ります。 フル動画はページ下部でご覧いただけます。 インタビュー内容 Shimizu:皆さんこんにちは、ロバート・ウォルターズの清水です。本日は海外留学プログラムを提供しているEF社の荒木れいなさんに、「キャリアに活きる留学
もっと読むビジネス環境が急速に変化する中、キャリアも進化する必要があります。今は転職を考えていないかもしれませんが、あなたのスキルや経験を最大限に活かすチャンスを逃していませんか?転職は、キャリアアップや新しい刺激、柔軟な働き方を手に入れるための一つの道です。そして、忙しいビジネスパーソンでも、転職エージェントを活用することで効率的かつ戦略的にキャリアを進めることができます。 キャリアの未来を考えるとき、可能性を広げる選択肢の一つとして、ぜひ転職を視野に入れてみませんか? 現代のビジネス環境は急速に変化しています。テクノロジーの進化、グローバルな競争、リモートワークの普及など、多くの要因が企業と個人のキ
もっと読む海外から日本への帰国が決まったら、日本での新たな生活に向けて準備を進める必要があります。そんな引っ越しを控えている方のために、スムーズに準備を進めるためのタイムラインに沿った帰国ガイドをご用意しました。 帰国前の準備から帰国後の手続き、生活インフラの手配、ご家族がいる方に向けた幼稚園・保育園・学校探しや入学手続き、日本での仕事開始に向けた準備など、押さえておくべき要点をまとめています。 日本での新たな生活をスタートに向けて、さっそく準備を始めましょう。 ガイドへのアクセスはこちら *ロバート・ウォルターズでは海外から日本へ帰国して働くことを検討している方へキャリアサポートをしています。 海外か
もっと読む