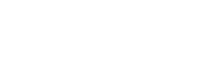オンライン面接で候補者と気まずい雰囲気にならないために
対面での面接と同じようにオンライン面接でも、候補者と採用マネジャー(入社後に所属する部署での上司)の双方にとって快適に面接を進められる環境を作れるか否かが、面接の生産性を大きく左右します。面接官となる採用マネジャーと候補者の対話が気まずいものにならないために、気を配るべきチェックポイントをまとめました。
イニシアチブを維持
オンライン通話での面接は、対面のときよりもイニシアチブを取りづらいような感覚を持つかもしれません。そういうときは、あらかじめ面接のアウトラインを決めておきましょう。順を追って会話を進め、時間内に聞き取りたい情報をひとつづつクリアし、売り込みたいこともしっかり網羅できるように努めることで、いつも通り主体的に面接を進められます。そうすれば、気まずい沈黙が生まれてしまう心配もなくなります。さらにはリラックスして会話を進めることで深く互いを知ることができるでしょう。
採用マネジャーの自己紹介&会社・役割を説明
面接は主に、候補者自身が自分のスキルを売り込み、その仕事・ポジションにいかに適しているかをアピールできる場です。しかし、日本のように人材不足の著しい市場では、採用マネジャー自身が会社・自分・チームを自己紹介し、対象となるポジションの役割や業務内容を説明することが重要です。そうすることで、候補者の不安や疑問を解き、スムーズに対話を進めていくことができるでしょう。
質問のバランスに注意
いうまでもなく面接では、採用マネジャーからの質問をもとに候補者一人ひとりが備えているハードスキルとコンピテンシーを計っていきます。しかし、人材不足による売り手優勢の転職市場にある日本では、自らの価値観と応募先企業の企業文化・社風との相性を気にする候補者が増えています。趣味や一般的な関心事を尋ねることでワークライフバランスへの考え方や価値観もわかります。このことを念頭に置いて、あなたの質問への回答から、その候補者が新しい仕事・長期的なキャリアに何を求めているかを素早く察知し、転職の動機づけになり得るものを積極的に売り込めるようにしましょう。ここで気をつけたいのがバランスです。先に挙げたスキル・コンピテンシーを判断するための質問と価値観・企業文化との相性をお互いに判断するための質問との割合を予め想定しておくことで、脱線し過ぎることや重要な項目の聞き逃しを避けましょう。
面接の終わりに次のステップを示す
面接の終わりには候補者にフィードバックを提供しましょう。候補者が優秀な人材であればポジティブな印象を残しておくことが大切です。このときの対応が企業イメージとして候補者に捉えられることもしばしばあります。面接で候補者に対してどんな印象を得たのか、次の選考プロセスに進められそうなのであれば、話せる範囲でいいので感触を伝えておきましょう。オンライン通話での面接でも、対面での面接の最後に握手で締めくくるようにポジティブな雰囲気で面接を終えることを意識してみてください。
関連コンテンツ
すべて見る製造 自動車 自動運転、コネクテッドカーなど技術の進化が期待される自動車分野では、コンポーネント/テストを担うソフトウェアエンジニア、電気エンジニアの採用が活発で、当社で扱う求人数、採用成立件数ともに当社開業以来最高の水準に達しています。2018年は自動車関連メーカーの多くが自社に開発担当者を据えはじめ、同時にサプライヤーが完成車メーカーにオンサイトエンジニアを常駐させる動きも広がっています。また大手メーカー各社がサプライヤーの見直しを進めたことにより1次サプライヤーでは営業体制を強化する動きが見られ、営業スペシャリスト、新規開拓(ビジネスデベロップメント)スペシャリストの採用が増えています。
もっと読むバイリンガルの人材獲得スペシャリストの不足が続き、特にジュニアからミドルレベルの人材需要が高まりました。特にプロフェッショナルサービス、IT、ヘルスケア分野でこの傾向が強く、2017年も採用担当者不足が続くでしょう。 戦略的人事を担うHRBP(ヒューマンリソース・ビジネスパートナー)やゼネラリスト、ジュニアレベルの給与スペシャリスト、ミドルからシニアレベルの報酬・福利厚生マネージャーの求人が多く、2016年は転職者の給与水準が 5 ~15%上昇しました。 バイリンガルの人事プロフェッショナルの需要が強まるなか全ての専門分野で深刻な人材不足が発生しており、この傾向は 2017年も続くと予想されま
もっと読む優秀な人材を採用するため、「エグゼクティブサーチ」を利用する企業が増えています。エグゼクティブサーチとは、企業の経営幹部など重要なポジションを担える人材をピンポイントで探し出す採用の手法のこと。今回は、エグゼクティブサーチが適している採用の目的や、エグゼクティブサーチの特徴、一般的な人材紹介との違いなどを解説します。 エグゼクティブサーチ とは ? エグゼクティブサーチとは、企業の経営に関わる経営幹部職(エグゼクティブレベル、「C-Level」人材)を採用する際に用いられる手法の一つで、優秀な人材をピンポイントで探し出す採用手法です。また、法務・会計などの高度な専門スキルを有したスペシャリスト
もっと読む