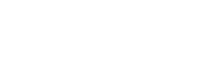成果主義に求められることとは
日本では従来から定着していた年功序列の人事制度に代わり、成果主義による人事制度の導入が広がってきています。そこで、成果主義とはどのような人事制度なのか、また日本企業における成果主義の定着状況などについて解説します。さらに、どのような人が成果主義を導入している企業に向いているのかについても見ていきましょう。
成果主義とは?大切なのは結果と過程
成果主義とは、業務の成果やその成果に至るまでの過程に対する評価によって給与や昇格などを決定する人事制度です。成果主義は結果のみを重視する実績主義と混同されがちですが、成果に至るまでのプロセスも合わせて評価される点で異なるものです。
成果主義の下では、年齢や勤続年数などによって待遇が決められるのではなく、成果を上げることが昇給や昇格につながるため、社員のモチベーションの維持、生産性の向上につながると考えられています。
成果主義のメリット
成果主義は結果主義ではない
まず、成果主義のメリットとしては「評価の公平性」が挙げられます。単なる結果主義だけで社員を評価してしまうと、「担当業務の難易度」が無視されがちです。簡単な仕事で100%の達成率を記録した社員は、難しい仕事で80%の達成率を記録した社員よりも無条件で評価されてしまうでしょう。また、社員が長期的なプロジェクトを担当しており、すぐに結果が出なくても会社の将来に大きく貢献している場合も、評価対象から外されてしまいます。成果主義は、業務の過程まで会社が評価することで公平性を保ちます。
給与(人件費)が効率化される
給与などの人件費が効率的になるのも成果主義のメリットです。多くの会社では単に「役職」や「キャリア」などの基準で給料が決まっています。しかし、こうした傾向が強くなりすぎると、「成果を挙げているのに給料が増えない」社員が現れるため、モチベーション維持が難しくなります。成果主義は、社員の評価を数値などによって分かりやすくするため、人件費の割り当てをスムーズに行うことができます。
働き方が効率化される
そして、成果主義が浸透すると、社員の働き方にも変化がでてきます。たとえば、「仕事は終わっていても早く帰ると評価が落ちるのではないか」などの理由から、無駄な残業、休日出勤を繰り返す社員もいます。しかし、こうした行動は残業代の増加へとつながり、結果的には会社に損害を与えます。成果主義によって評価軸が定まっていれば、「成果に伴わないような残業はしない」との共通認識が社内に広がり、無駄な休日出勤や残業を減らすことができます。
成果主義のデメリット
数々のメリットがある一方で、成果主義にはデメリットもあります。
成果が可視化しにくい部署の評価
会社として成果主義を採用される可能性がある場合、「評価軸の設定が難しい部署もある」ことは認識しておきたいポイントです。営業部やマーケティング部などは成果を数字に置き換えられるため、比較的評価は容易です。しかし、「人事部」や「営業支援」などの方は成果を可視化しにくい場合が出てきます。こうした部署に成果主義を採用した場合、成果主義が適用されると他部署よりも評価を低くなってしまう可能性があり、公平性が崩れる場合があります。
従業員の定着率への影響
「社員の定着率への影響」も懸念するべきポイントでしょう。成果主義では、有能な人材ほど給料や出世に仕事ぶりが反映されるので、モチベーションが高まります。しかし、逆に思うような成果を挙げられなかった人材は、同僚に差をつけられてしまいます。
その結果、モチベーションを失ったり、会社に見切りをつけて転職したりする従業員が出てくるでしょう。成果主義はすべての社員にとって歓迎される方式ではないということは押さえておいたほうがいいでしょう。
評価されないことはしないという風潮
「効率性だけが重視されるようになる」リスクも発生する可能性があります。成果主義では、評価軸が明確であるがゆえに、「評価されない仕事はしない」という発想を招きがちです。営業部でいえば、数字を重視するがあまり、新規開拓などの業務がおろそかになってしまったり、数字が上がっているから自分はいいんだと、報告書の作成といった数字にはつながらない業務を怠るといったことも出てくるかもしれません。
チームワークの乱れ
また、同僚の業務に関心を抱かなくなり、チームワークが乱れることもありえます。行き過ぎた成果主義の会社では、「自分の仕事はあくまで自分の担当している部分に限る」という考えが主流になりがちです。そのため、上司や同僚、部下ですらライバルととらえ、サポート意識が薄まっていくのです。その結果、新人教育を積極的に引き受けるような先輩社員が少なくなり、若手が育たなくなっていきます。社員同士の結束力も弱く、トラブルがあったときにもろい側面をのぞかせることもあります。
社内行事にも仕事に関係ないからと出席しないということもあるかもしれません。そうなると会社のカルチャーがどんどん崩れていってしまう可能性があることも把握しておくべきでしょう。
部下を成果主義で評価をする時に失敗しないポイント
成果主義を導入しても、かえって社内が混乱するケースもありえます。なぜなら、準備ができていない状態で成果主義を始めようとしても、社員に受け入れられないからです。成果主義による人事評価で失敗をしないために、注意点をしっかり踏まえておきましょう。
評価者のトレーニングを行う
たとえば、「評価者のトレーニング」は重要です。成果主義は主観をまじえず、社員の仕事ぶりを客観的に評価する方式です。しかし、評価者も人間である以上、感情的に社員を評価してしまう危険は消えません。「付き合いがいいから」「明るくて楽しい部下だから」などのひいき目が入ってしまうこともありえます。
評価者には成果主義の基本を研修などを行い、新しい価値観に慣れてもらうことが必要です。そして、本当に客観的な評価が下されていったのか、経営陣が「評価者を評価する」ようにも努めましょう。
また、成果主義にも「臨機応変な対応」を織り交ぜることは大事です。営業職以外の、数字で評価されない部署の人たちの評価を定め、ときには「売上」や「目標達成率」では計れない貢献度を見極めていきます。成果主義の導入によって、一部の部署だけが活気づき、他の部署がやる気を失ってしまうような事態にはならないよう気をつけましょう。
日本企業に多いのは?成果主義と年功序列の違い
日本の企業では、年齢や勤続年数に応じて給与額や役職が上昇していく年功序列による人事制度が根付いていました。しかし、1990年代のバブル経済崩壊以降、低成長経済の下で会社が年功序列型の賃金体系を維持することが難しくなってきたことを背景に成果主義への移行も進んできています。
しかしながら、日本では成果主義が実質的には定着していないともいわれています。成果主義を導入している企業においても、実際には労働時間の長さで評価がなされているなどの指摘があるのも現実です。また、成果主義は短期的な結果にのみ目を奪われて、会社の長期的な成長のための行動に結びつかないなどの問題も認識されるようになってきています。売上以外の成果を数値化することの難しさや、個人の成績のみを追求することによる人間関係の悪化など、成果主義の弊害も強調されるようになってきているのです。
そのため、日本において完全な形で成果主義を運用している企業は少なく、さまざまな修正を加えて人事制度を運用していることがほとんどです。
成果主義と能力主義の違い
成果主義と混同されがちな評価方式が「能力主義」です。能力主義とはつまり、「仕事をするうえでのスキルを評価する」ことです。純粋な売上や達成率は、人事評価においてさほど優先されません。結果だけでなく、仕事をするうえでのプロセスも重要になるため、どう仕事を遂行したのかが深く問われます。
能力主義の基本をなすのは、評価者による「査定」です。一度査定が終わると、基本的には担当業務や部署によって社員の評価は変わりません。イメージとしては日本企業で例えば係長の方が一度査定を受けて再度係長であれば、評価はそのままです。仮に部署が異動になったとしても係長であることが多いでしょう。こうした特性は「異動の際の不満を防止できる」などのメリットにもつながるでしょう。
その結果として、能力主義は社員の定着率を高くするなどの側面も見られます。一度、会社から下された評価はすぐにくつがえらないため、短期的な仕事の成果、売上を気にしなくても働き続けられます。また、上層部に強いコネクションを築けた人は、キャリアアップが有利になるのも大きなポイントでしょう。
能力主義のデメリット
能力主義のデメリットとして挙げられるのが、「定義が曖昧」という点です。何をもって「能力が高い」とするかは、企業ごとに大きく異なります。「目標達成率」や「取り組む仕事の難易度」という分かりやすい基準がないため、往々にして評価者の主観によって評価が定まってしまいがちです。さらに、「能力主義では数字をどの程度考慮するか」についても異論があり、この点についてもやはり、明確な評価方法は決まっていません。能力主義では「評価の理由に納得ができない」と感じる社員も多く、会社側が他の評価方式も柔軟に併用するケースも出てきています。
成果主義が向いている人の特徴とは
成果主義を導入している企業で働くことに向いている人もいれば向いていない人もいます。出世に興味がなく、のんびり仕事をしたい人には成果主義を導入している企業は向いていないでしょう。
一方、自分の実力を試したい人、常に自分を磨いて向上していきたいと考えているような人には、成果主義は最適な人事制度です。自分の実力次第で短期間で給料を上げていくことも可能なので、モチベーションの維持・向上にも結びつきます。
ただ、現在の日本企業は成果主義の最適な運用方法を模索している段階で、各企業によって運用の仕方はさまざまです。「成果主義」という言葉だけでなく、実際に運用方法についても確認をした方が良いでしょう。
関連コンテンツ
すべて見る人口の減少と高齢化により、多くの産業で労働力不足が進行している日本。 2023年の有効求人倍率は平均で1.31倍となっており、優秀な人材の採用がますます困難になっています。 その中でも、日本は特にグローバル人材不足という課題も抱えており、国民の英語力の低さや留学者数の減少により希少なグローバル人材の獲得競争が加速する状況に。 このような状況を踏まえ、企業が高い知識と語学力を兼ね備えたグローバル人材を獲得するためにはどのようなポイントを押さえるべきなのでしょうか。 以下の資料をダウンロードして、貴社の採用戦略のヒントにご活用ください。 ダウンロードはこちら
もっと読む採用審査では、面接での結果が決定打になることが多いでしょう。しかし、在宅勤務のときなど、対面での面接ができない場合もあります。候補者を会社に呼んで直接面接するのに代えて、オンライン通話システムで面接をすることもできます。このように、採用審査のプロセスのなかには、デジタル化できるものが複数あります。採用審査の流れを詳しく紐解いてみることで、普段は当たり前だと思っていたプロセスを効率化できるだけでなく、より迅速に進められるかもしれません。求人を素早く広告する、応募の中から候補者を絞り込む、企業ブランディングも同時に叶える――。この記事では、採用担当者のあなたが、対面での面接ができない時期にも、リモ
もっと読む企業にとって、人材を採用する際の悩みの種は、カルチャーフィットする人材を採用するのか?それとも多様な人材を採用するのか?ということにあるのではないでしょうか? 社風があっていて、価値観を共有できる人材の採用は、自動的に高いパフォーマンスをもたらすのでしょうか?それとも、多様な人材がもたらす影響はより企業へ利益をもたらすのでしょうか? ロバート・ウォルターズでは、 採用担当者 Pernod Ricardとのパネルディスカッションで、これらの疑問を探りました。 調査結果と業界の知見からわかったこと スキルセット、性別、年齢などの面で多様な従業員がいれば、「同じようなチーム」ではなくなるため、より革
もっと読む