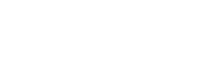ダイバーシティ&インクルージョンを実現した組織の強みとは?
ダイバーシティ&インクルージョンを重要視する企業が増えています。ダイバーシティ&インクルージョンとは、人材の多様性(=ダイバーシティ)を認め、受け入れて活かすこと(=インクルージョン)を意味します。一般的には、国籍や性別、年齢の多様性確保のことだと考えられていますが、企業の事業成長につながるようなダイバーシティ&インクルージョンを実現するには、上記で挙げたようなわかりやすい多様性を受け入れるだけでなく、メンバーそれぞれが異なる存在だと認識し、尊重する組織文化をつくることが大切です。
本記事では、ダイバーシティ&インクルージョンの本質に迫り、どのように実現していくべきかをまとめました。
ダイバーシティ&インクルージョン(以下D&I)とは
D&Iはダイバーシティとインクルージョンを組み合わせた概念で、「多様性を認め、受け入れて、活かすこと」と定義できます。
性別、年齢、国籍、宗教、ソーシャルヒエラルキー、障害の有無、性自認、雇用形態(正社員、契約社員、派遣社員)、ライフステージ、価値観、世代といった違いを単に認め受け入れるだけでなく、企業・組織として相乗効果を発揮するように活かしていくのがD&Iの目指す姿です。
このD&Iは1964年に、アメリカで社会的な差別の是正のために、年齢・性別・人種などによる一切の差別を禁止する「新公民権法」が施行されたことをきっかけに生まれた概念ですが、2000年以降日本でも、ITの急速な発展やグローバル化を背景に、制度として取り入れる企業が増えています。
日本で導入が遅れている背景
日本ではD&Iの実現が遅れていると言われますが、その背景の一つに「メンバーシップ型雇用」が根付いていることが挙げられます。
メンバーシップ型雇用では、従業員にはそれぞれの専門性や強み、個性を活かすスペシャリストではなく、ジェネラリストであることが求められます。それは高度経済成長期の企業には適した雇用の仕組みであり、企業が急速に成長していくためには、効率的に長期的な労働力を育てることが必要不可欠でした。そのため、ひとつの企業が一括で大量の人材を採用し、誰かが欠けても、社内から配置転換で補えるように、人材育成をしてきました。結果的に、同じような属性・勤務形態・価値観の人たちと長期的に働くことが前提になっており、同質性が強い組織になりやすくなっています。
D&Iを実現するための動き
そういった同質性の高い組織において多様性を実現するため、女性活躍推進に続いて日本で当初導入されたのは障がい者、シニア層、LGBTに関する制度が中心でしたが、最近では雇用形態や新卒一括採用などの枠組みを外す制度を導入する企業も増えてきました。
例えば、それまで雇用形態で決まっていた給与体系に対し、他社に先駆けて同一労働・同一賃金の制度を導入し、雇用形態に関わらず同じ職務に対して、同じ賃金を支払うようにし、雇用形態による格差をなくす取り組みがされた大手外資系企業もあります。この会社では、さらにパートタイマーの正社員化も実現し、働いている時間の長さに関わらず同じ福利厚生を提供しています。また、別の大手企業では、多様な人材を採用するために、学生だけでなく、社会人や障がい者向けのインターンシップを行うことで、平等に雇用の機会を与えています。
その他、女性の管理職を育てるため、女性の雇用比率を上げるために、子育て中の方でも働きやすいような時短勤務制度、テレワーク、育休制度などを導入する企業も急増しています。
インクルージョンを実現するために必要なこと
インクルージョンが実現されると、雇用形態や属性に関係なく活躍する場が生まれるため、多様な能力を伸ばす企業文化になり、結果として従業員のエンゲージメントが高まる、イノベーションが起きやすくなる、組織のパフォーマンスが向上するなどの効果が期待されています。
制度をつくることで、ダイバーシティへの姿勢・取り組んでいることを表明できますが、制度づくりだけではインクルージョンの定義である「受け入れられ、活かされている」が満たされたことにはなりません。真のD&Iを実現するためには、上記で挙げたダイバーシティを認める制度に加えて、社内の文化や考え方を変革していくことも必要不可欠です。では、具体的にどのように取り組んでいけばよいのでしょうか。4つのアプローチについてまとめました。
1.リーダー・人事がD&Iの必要性を認識する
従業員の模範となるよう、リーダー・人事が率先して体現することから始めましょう。まずは、「ダイバーシティの推進は事業成長の手段である」という認識のもと、何のために実施するのかという目的や事業上の必要性を明確化し、数値的な結果にも結び付いていることを理解することが大切です。
2.アンコンシャスバイアスを外すトレーニング・施策を実施する
アンコンシャスバイアス(無意識バイアス)とは、性別、年齢、人種などで、無意識に偏見を持って他人を評価してしまう行為を指します。
海外の企業では、このアンコンシャスバイアスを外したり、偏見に対してアクションを取るトレーニングを行っています。最近では日本でも経営層向け、管理職向け、全社員向けなど、それぞれの階層や立場に合わせたトレーニングを用意し、全社員のインクルージョン・スキルを高めている企業事例が増えています。
また、アンコンシャスバイアスを外すためのポリシーや制度を整備している企業もあります。例えば、「一切の差別禁止」という方針を掲げて、入社時に研修を行う企業もあります。ほかには、制度として「男女間での給与における差別禁止」「プロセスおよび達成した成果で評価」「エンゲージメントサーベイ(従業員意識調査)の実施」を整備している企業も増えています。
3.心理的安全性が高いチームづくり
D&Iを推進するためには、意見を言いやすい心理的安全性の高いチームづくりが必要不可欠です。心理的安全性が低い組織では、多様な人材が能力を発揮することは困難です。社内の風通しを良くし、心理的安全性を高める取り組みとして、カジュアルコミュニケーション活性化施策を導入するのも有効です。
カジュアルコミュニケーションは、一般的に業務に直接的に関係のない会話を指します。リモートワークを取り入れている場合は、オンラインでカジュアルコミュニケーションをとる方法を考えましょう。例えば、チャットツールで雑談専用のチャンネルをつくる、こまめにビデオ通話で1on1の時間をとるといった方法などが挙げられます。
せっかく多様な意見を引き出し成果につなげていても、一部の社員にしか共有されていなければ、全体の意識向上や一体感にはつながらないため、意見や情報共有の方法も検討が必要です。例えば、ロールモデルとなる人材の活躍を社内に周知するなどの取り組みも有効です。
4.コンフリクト・マネジメントを行う
意見が出やすくなり議論が活発になると、次に課題となるのがコンフリクトです。コンフリクトは、意見の相違や対立が感情的な衝突となってしまうことを指します。ですが、コンフリクトは適切にマネジメントをすることで、イノベーションを生む、組織活性化のきっかけとすることもできます。
コンフリクト・マネジメントについてはこちらでも詳しく解説しています。
このように、単に制度をつくるだけでなく、コミュニケーションのあり方を見直すことで、「多様性を認め、受け入れて、活かす」というD&Iの下地が出来上がることが期待されます。
優秀なグローバル人材をお探しですか?
お電話またはこちらからご相談下さい。 経験豊富なキャリアコンサルタントが最適な人材を紹介します。
- 03-4570-1500
- info@robertwalters.co.jp
関連コンテンツ
すべて見る人口の減少と高齢化により、多くの産業で労働力不足が進行している日本。 2023年の有効求人倍率は平均で1.31倍となっており、優秀な人材の採用がますます困難になっています。 その中でも、日本は特にグローバル人材不足という課題も抱えており、国民の英語力の低さや留学者数の減少により希少なグローバル人材の獲得競争が加速する状況に。 このような状況を踏まえ、企業が高い知識と語学力を兼ね備えたグローバル人材を獲得するためにはどのようなポイントを押さえるべきなのでしょうか。 以下の資料をダウンロードして、貴社の採用戦略のヒントにご活用ください。 ダウンロードはこちら
もっと読む採用審査では、面接での結果が決定打になることが多いでしょう。しかし、在宅勤務のときなど、対面での面接ができない場合もあります。候補者を会社に呼んで直接面接するのに代えて、オンライン通話システムで面接をすることもできます。このように、採用審査のプロセスのなかには、デジタル化できるものが複数あります。採用審査の流れを詳しく紐解いてみることで、普段は当たり前だと思っていたプロセスを効率化できるだけでなく、より迅速に進められるかもしれません。求人を素早く広告する、応募の中から候補者を絞り込む、企業ブランディングも同時に叶える――。この記事では、採用担当者のあなたが、対面での面接ができない時期にも、リモ
もっと読む企業にとって、人材を採用する際の悩みの種は、カルチャーフィットする人材を採用するのか?それとも多様な人材を採用するのか?ということにあるのではないでしょうか? 社風があっていて、価値観を共有できる人材の採用は、自動的に高いパフォーマンスをもたらすのでしょうか?それとも、多様な人材がもたらす影響はより企業へ利益をもたらすのでしょうか? ロバート・ウォルターズでは、 採用担当者 Pernod Ricardとのパネルディスカッションで、これらの疑問を探りました。 調査結果と業界の知見からわかったこと スキルセット、性別、年齢などの面で多様な従業員がいれば、「同じようなチーム」ではなくなるため、より革
もっと読む