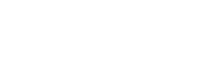「ジョブ型」導入後に、チームワークを最大化させる4ステップ
近年、日本国内の企業でも「ジョブ型」雇用を導入する事例が増えてきています。ジョブ型雇用は、今まで日本企業が行ってきたメンバーシップ型雇用と異なり、職務内容を明示し、その職務内容に対して仕事を行う雇用のあり方です。欧米を中心に行われてきたジョブ型雇用ですが、チームワークへの懸念から導入に躊躇するケースもあるといいます。メンバーシップ型雇用で形作られていた組織、企業文化に、そのままジョブ型雇用の仕組みを導入すればミスマッチが起きかねないでしょう。ジョブ型雇用を導入しながら、チームワークを最大化させて成果を上げるために、企業の組織・文化をどのように変えるのがいいのでしょうか。
組織への帰属が問われる「メンバーシップ型」、仕事の専門性が問われる「ジョブ型」
これまで日本の企業で一般的だった雇用形態は、「メンバーシップ型」雇用と呼ばれます。どんな仕事をするのかは、入社時にはあまり決まっておらず、会社に定年まで勤めることが前提で(終身雇用)、会社がさまざまな職種を経験させる異動を行い(ジョブローテーション)、会社が従業員を長期的に育成していきます。従業員は、雇用の安定が得られやすいですが、専門的なスキルを身につけにくくなります。
一方で、「ジョブ型」雇用とは、職務(ジョブ)の内容や、必要な知識やスキル、経験、資格などの専門性が明示された雇用を指します。仕事に関する具体的な内容と条件が、「ジョブディスクリプション」(職務記述書)にまとめられ、求職者はそれを見て応募します。ポジションに対して人を充てるため、その職に就く従業員には、その職種が求める専門性が要求され、自身の専門性を高めることができます。欧米企業で一般的な雇用形態です。
メンバーシップ型雇用は、従業員には専門性よりも、組織への帰属意識が求められます。「その組織の一員である」意識を持つことが、何よりも優先されます。新卒一括採用と終身雇用制度のもと、組織内でジョブローテーションを繰り返して昇進していくこの仕組みは、人材補充を社内で行えるという利点があります。欠員が出たら、部署内や他部署から人を充てることで解決できます。その際必要となるのは、どのポジションであろうとその組織のためならば、異動を受け入れ、働いてくれる人材です。すると、メンバーシップ型雇用には、このポジションしかできないという専門性を持った人材よりも、どんなポジションでも異動可能なジェネラリスト人材が重宝されることになります。
反対にジョブ型雇用で重視されるのは、そのポジションに対する専門性です。欠員が出たら、その職に必要な専門性を備えた人材を募集することになります。社内にその人材がいなければ、当然社外から募集することになります。ジョブ型雇用の人材は、その職種に対するプロフェッショナルであり、ジェネラリストよりもスペシャリストとなります。ジョブ型雇用は、新卒一括採用終身雇用制度とジョブローテーションに支えられたメンバーシップ型雇用とは真逆の、人材流動性が高い労働市場を前提とした制度と言えます。
しかし、今、日本企業で、ジョブ型雇用を取り入れる動きが出てきています。それは一体どうしてでしょうか。
今「ジョブ型」雇用を導入する企業が増えている理由
コロナ禍でテレワークが進んだということも要因の一つですが、ずっと以前から日本企業がジョブ型雇用を導入する動きがあります。その最大の理由は、グローバル化とテクノロジーの進展です。グローバル化の進展で国内市場は国外市場と直結するようになり、日本企業は海外の企業と競争していかなければならなくなりました。すると、企業には高度な専門性をもった人材が必要となってきます。海外のカウンターパートがその職種で何十年も経験を積んだエキスパートである時に、日本側が数ヶ月前に関係ない部署から異動になった人材ということでは太刀打ちができません。
また、テクノロジーの急速な発展とグローバル化により、ビジネスの迅速化が進んでいます。別部署にいた人材を社内で再教育し、別部署に配置転換を行うのでは、このビジネス環境で要求されるスピードについていけないという支障が起きています。例えば、今まで現場で配線の接続を行うエンジニアが、プログラミングを行うエンジニアに配置転換になった場合、コンピューターサイエンスの大学院で博士号をもった海外のエンジニアに太刀打ちできるとは到底考えられません。すると、今までメンバーシップ型雇用が支えてきた、ジェネラリスト型の人材育成・配置では対応できず、高度な専門性を持った人材の獲得と配置が必要となってきました。新卒一括採用や終身雇用をやめる動きは、この社会情勢の変化と軌を一にしています。同一労働同一賃金ルールの導入や年功序列型賃金制度の改定もその流れにあります。
こうした背景のなか、ハイブリッド型勤務も広がり労働時間ではなく成果で評価する必要性が高まっていることから、ジョブ型雇用のほうが相性がよいとして注目されています。
ジョブ型雇用を導入した日本企業の事例
実際にジョブ型雇用の導入を決定した2社について紹介します。
ある国内大手メーカーでは、国内で働く16万人を含め世界中の従業員30万人をジョブ型の人事制度に転換しました。能力と意欲に応じた適所適材の配置によって、個人と組織のパフォーマンスを高め、生産性向上やイノベーションにつなげる狙いです。それに伴い、300〜400種類のジョブ・ディスクリプションを用意する、人材の能力の可視化のため「タレントレビュー」を行うなど、さまざまな刷新を進めています。
ある国内大手通信会社では、コロナ禍を受け「社員一人ひとりが時間や場所にとらわれず成果を出す働き方を実現する」ことを掲げ、その一貫として、ジョブ型雇用を推進していくことにしました。市場価値に基づく報酬制度や専門性の向上を実現するのが目的です。
2社とも、コロナ禍や人材市場のグローバル化を受け、個人の能力・専門性の向上を目的として、ジョブ型雇用の導入を進めていることがわかります。
日本企業が「ジョブ型」雇用を導入しても上手くいかない?
こうしてみると、すぐにジョブ型雇用に切り替えればいいように思われますが、日本企業がジョブ型を導入しようとしてもなかなかうまくいかないという話を耳にすることがあります。懸念理由としてしばしば挙げられるのが「チームワークの希薄化」です。ジョブ型雇用は個人で成果を上げていくスタイルになるため、結束力が育まれづらく、チームワークが機能しなくなってしまうのではないかという懸念です。これはメンバーシップ型の組織に、無理やりジョブ型雇用を導入しようとしたから起きることだと言えます。
メンバーシップ型組織のメリットは、個々の役割が明確ではないがゆえに、他の人の仕事をチームでカバーできるという点があります。ジョブ型組織にしたら、みな自分の仕事しかせず、チームが崩壊してしまうのではないか、そんな懸念を抱く人もいるでしょう。それでは、ジョブ型雇用を採用している欧米企業はチームワークがないのかというと、決してそうは見えません。メンバーシップ型のチームワークと、ジョブ型のチームワークとでは、どこが異なるのでしょうか。
「ビジョン」と「エンゲージメント」が鍵
「メンバーシップ型」組織では、従業員は組織への帰属意識があることが前提ですから、「私はなぜこの組織にいたいのか」といった問いを、自身に問い直す機会がありません。自分がその組織にいつづける前提で、「組織のために役に立つこと」を追求する仕事のスタイルになるでしょう。
「ジョブ型」組織では、従業員に組織への帰属意識の前提はありません。「私はなぜこの組織にいたいのか」を、各自が常に問い直し、その結果「私はここで働くことが最適である」という意思を持つことが必要です。そこで欠かせないのが、会社が事業を通じて社会や市場に対して成し遂げたいこと(ビジョン)への共感と、自分の成長と会社の事業の成長が一致していると考えること(エンゲージメント)です。
「ビジョン」への共感と、「エンゲージメント」の感覚があることで、「私がこの会社で働き事業を成長させることは、社会や市場に対して価値をもたらしているし、私自身が成長することにも繋がっている」という意識を、各従業員が持つことが重要です。この意識は「事業を成長させるためには、自分は何ができるか」という考えへと発展し、チームワークを重んじながら自らの専門性を最大限発揮して会社の成長に貢献しようとい努力に繋がります。
「メンバーシップ型」組織のチームワークが「組織の役に立つ」というチームワークだとすると、「ジョブ型」組織のチームワークは「組織ではなく、事業成長のために貢献する」というチームワークであると言い替えられるでしょう。
「ジョブ型」雇用をチームとして機能させるために必要な4つのステップ
ジョブ型雇用をチームとして機能させるために欠かせない「ビジョンの共有」と「エンゲージメントの強化」について、そのための4ステップを紹介します。
① 仕事やプロジェクトの社会的意義・ゴールを共有し、マイルストーンを明確にする
メンバーの認識を一致させるため、企業の事業目的や社会的意義、ゴール、そこまでのマイルストーンを日常的に共有します。フォーマルな会議形態でなくとも、カジュアルに意見を交わせるフォーカスグループ・ディスカッションやオフサイトで共有した方が、意見が活発に出やすく、認識を摺り合わせやすいでしょう。
② 1on1を通じて、個人の目標・成長と会社の目標・成長を擦り合わせる
ゴールに向かう過程で、困っていること・課題感を1on1ミーティングを通じて上司と共有します。上司には課題を把握し、会社の目標・成長と擦り合わせるようなコミュニケーションが求められます。
③ 困りごとに対して、お互いのできること、強みを共有する
ビジネスの場では個人の知見だけでは解決できない課題がほとんどです。困りごとや課題に対しては、上司・部下、チームメンバー同士が相互で知恵を共有し、それぞれ自分の強み(自分のプロフェッショナル分野)を活かして解決策を一緒に練りましょう。他者と連携し合って仕事を成し遂げれば、チームワークの意義がメンバーに浸透しやすくなります。
④ 成功体験を共有し、お互いをたたえ合う
毎月、半年ごとなど定期的に、メンバー同士でゴールに向けたプロセスにおける達成感や成功体験を共有しましょう。自分たちがやってきたことの大義を改めて認識でき、モチベーションの向上にもつながります。人と協力して推進したことで成し遂げられた仕事の大きさや得られたメリットを共有すると、その後もチームワークを意識づけることができるでしょう。
関連コンテンツ
すべて見る人口の減少と高齢化により、多くの産業で労働力不足が進行している日本。 2023年の有効求人倍率は平均で1.31倍となっており、優秀な人材の採用がますます困難になっています。 その中でも、日本は特にグローバル人材不足という課題も抱えており、国民の英語力の低さや留学者数の減少により希少なグローバル人材の獲得競争が加速する状況に。 このような状況を踏まえ、企業が高い知識と語学力を兼ね備えたグローバル人材を獲得するためにはどのようなポイントを押さえるべきなのでしょうか。 以下の資料をダウンロードして、貴社の採用戦略のヒントにご活用ください。 ダウンロードはこちら
もっと読む採用審査では、面接での結果が決定打になることが多いでしょう。しかし、在宅勤務のときなど、対面での面接ができない場合もあります。候補者を会社に呼んで直接面接するのに代えて、オンライン通話システムで面接をすることもできます。このように、採用審査のプロセスのなかには、デジタル化できるものが複数あります。採用審査の流れを詳しく紐解いてみることで、普段は当たり前だと思っていたプロセスを効率化できるだけでなく、より迅速に進められるかもしれません。求人を素早く広告する、応募の中から候補者を絞り込む、企業ブランディングも同時に叶える――。この記事では、採用担当者のあなたが、対面での面接ができない時期にも、リモ
もっと読む企業にとって、人材を採用する際の悩みの種は、カルチャーフィットする人材を採用するのか?それとも多様な人材を採用するのか?ということにあるのではないでしょうか? 社風があっていて、価値観を共有できる人材の採用は、自動的に高いパフォーマンスをもたらすのでしょうか?それとも、多様な人材がもたらす影響はより企業へ利益をもたらすのでしょうか? ロバート・ウォルターズでは、 採用担当者 Pernod Ricardとのパネルディスカッションで、これらの疑問を探りました。 調査結果と業界の知見からわかったこと スキルセット、性別、年齢などの面で多様な従業員がいれば、「同じようなチーム」ではなくなるため、より革
もっと読む