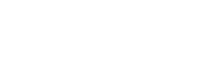転職面接のお礼メールは逆効果?送る時に必要なマナーと書き方・例文も紹介
面接が終わった後に、悩むのが企業へ送る「お礼のメール」。送るとむしろ逆効果になるのではないかと不安に思う方も多いのではないでしょうか。今回は転職における面接後のお礼メールについて解説。例文を交えて面接のお礼メールの必要性と送る時のマナーについてご紹介します。
面接後のお礼メール例文
①タイトル・件名 【面接の御礼】〇月〇日:(自分の氏名)
②宛先・担当者の名前を明記 【会社名】○○株式会社 【部署】○○部○○課 【相手の名前】△△ △△様
③挨拶 お世話になっております。 私、本日○○時に面接いただきました、□□と申します。 本日(または先日)はご多忙の中、面接のお時間をいただき誠にありがとうございます。
④主文 △△様からお話を伺う中で、貴社の取り組んでいるプロジェクトへの理解が深まりました。その実現のため、身に付けていくべきスキルや今後のビジョンがより明確になり、一層の志望意欲が高まりました。 それと同時に私の○○という経験は貴社の◇◇といった方針とマッチすると確信しております。 ⑤文末・結びの言葉 取り急ぎ、お礼を申し上げたくご連絡させていただきました。 ご多忙かと存じますので、ご返信には及びません。 本日は、誠にありがとうございました。 末筆ながら貴社のますますの発展をお祈りしています。
⑥署名 【氏名】 □□ □□ 【電話番号】○○-○○○-○○ 【メールアドレス】××@××.jp |
面接お礼メールの送り先一覧
| 宛先 | ポイント | |
| 個人面接 | 採用担当者や人事宛 | 名刺などをもらっている場合は、面接官に直接送りましょう。 |
| 集団(グループ)面接・複数面接 | 代表者一名への送信 | 「担当者様」というように一括りの表記をしましょう。「各位」という表現は社内宛てで、不適切な表現であるため使用を控えましょう。 |
| 送るべき相手の名前やアドレスが分からない | 企業HP掲載のメールアドレス宛 | 「採用担当者様」と表記しても構いません。名前が分かる場合には「採用担当 ○○様」のように表記しましょう。SNSなどでの連絡は控えるのが無難です。 |
そもそもお礼メールは必要?
お礼メールを送るべきかどうかについて、明確な答えはありません。送らないからといって合否に直接な影響はないでしょう。しかし、熱意や感謝を伝えることができるため、稀に採用への後押しになることもあります。
お礼メールが逆効果の可能性は?
大企業では、応募者の多さや業務の忙しさから、メールを読む時間がなく迷惑と考える企業も多いようです。ほぼテンプレートの内容を使用して送信するのであれば、相手に「読む手間をかけさせられるだけ」と、捉えられかねないため送らない方が無難なこともあります。また、長文や分かりづらい構成のメールは、読むのに時間がかかり好まれませんので、注意しましょう。
既に先方とやり取りしている場合は?
面接当日の業務連絡などで、先方と既にやり取りをしているケースも十分に考えられます。また宛先に、担当者1人だけではなく複数人入っていることもあるでしょう。この場合には、既に連絡を取っている宛先に、全員返信で送信するようにしましょう。
もし面接官のメールアドレスがわからない場合
もし面接官の方々のメールアドレスがわからない場合、公開されている採用担当者宛のメールアドレスにお礼メールを送りましょう。
面接官が複数人だった場合は、「本日面接いただいた○○様に、くれぐれも宜しくお伝えください」といった文章を添えると良いでしょう。
ただあくまで一般的な話であるため、他の面接者へお礼メールを送っても構いません。「現場担当者と話が盛り上がった」「社長が中心に質問していた」などの場合は臨機応変に対応しましょう。
面接について、何かご質問等ございましたら、 どうぞお気軽にロバート・ウォルターズのキャリア・コンサルタントへご質問ください。
企業へのお礼メールで避けること
せっかくお礼メールを送ったとしても、逆効果になってしまうこともあります。そうならないためにも、NG例を確認しておきましょう。
緊張して話せなかったことを伝えるために長文メールを送る
面接で緊張していたために、伝えきれなかった内容をお礼メールに長文で書き込むことはやめましょう。お礼を伝える場にふさわしくなく、自分の至らなかった点を連絡することはマイナスの印象すら与えてしまいます。お礼メールでは、感謝を中心に伝えましょう。
緊張して話せなかったことをどうしても追加したい場合は1文程度に留めておくのが無難です。
同じ内容のメールを送信する(面接が複数回ある場合)
お礼メールは面接のたびに送信しても問題はありません。ただし、メールの内容が毎回同じにならないように気を付けましょう。
誤字脱字に注意
誤字脱字に注意し、メールを送信する前に内容をよく確認してから送りましょう。とくに相手の名前や部署の間違いは失礼に当たります。再確認を怠らないようにしましょう。また、スマホでメールを作成した場合は誤字脱字が増える傾向にあります。送信前の確認に十分な時間を使いましょう。
強調文字・色文字・下線などの過度な装飾を避ける
色文字や太字、下線を使用しての強調は基本使用しないようにしましょう。基本的にこうした装飾はビジネスの場ではふさわしくありません。受信側の設定によっては、正しく反映されず文字化けが起こる可能性も考えられます。
会社のアドレスを使用する
会社のメールアドレスを使用して応募先と連絡を取り合うことは控え、プライベート用のメールアドレスを使用しましょう。無用なトラブルへの発展を防ぐためです。
SNSからむやみに連絡を取る
SNSを個人的に利用している場合があり、会社へプライベートを持ち込まないようにしている人も多くいます。連絡先が分からない場合であっても、個人のSNSから連絡を取ることは避けましょう。もし、どうしてもメールを送りたい場合は、企業のホームページから企業宛てにメールを送信するのが無難です。
テンプレートのコピペ・丸写し
企業にとって、テンプレートを丸写ししたお礼メールは読むのに時間を取られ、かえって迷惑と感じます。お礼メールは自分の言葉で書くことが重要です。送るのであれば、テンプレートを基に自分の言葉でメールを作成しましょう。
かなり時間が経った後に送信
お礼メールを送信する場合には、面接が終了した当日、遅くとも翌日には送信しましょう。遅くなればなるほど、相手に不快感や不信感を与える可能性があります。なお、当日・翌日共に深夜の時間帯は避け、当日であれば社会人が勤務している時間帯までに、翌日であればメールのチェックをすることの多い朝の8時から9時が効果的です。
その他の方法でのフォローアップ
企業にとってメール以外でお礼を伝えることは、どのような印象を与えるのでしょうか?メール以外のフォローアップ方法とポイントを紹介します。
手紙
お礼の伝える手段の1つとして、手紙が挙げられます。「誠実性の現れ」と捉える企業もあるようです。しかし、手紙の場合は時差があり、二次面接などを控えていると、届くのが面接後になることがあるため注意しましょう。
電話でのフォローアップ
面接官から電話でのやり取りの指示がある場合以外は、メールでお礼を伝えるのが基本です。電話でのやり取りは業務への妨げが発生するので、お礼を電話で伝えることは極力避けましょう。
SNSを活用してみる
プライベートなアカウントへの連絡は基本的に失礼にあたります。しかし近年、企業によってはSNSでやり取りするケースも増えています。その場合は、SNS経由で面接のお礼をしましょう。またSNSでは、互いのプロフィールが見えてしまうため、自身のアカウントに不適切な内容がないかよく確認しておきましょう。
リファレンス(照会先)となってくれた人にコンタクトする
応募先企業からの回答を待っている間に、リファレンス(照会先)へ電話をすることは効果的です。リファレンスとなってくれた人が、あなたについてポジティブなコメントをしてくれるようにコミュニケーションを取り、過去にその人と業務を通じて共有した素晴らしい経験についてそれとなく思い出してもらいましょう。
一緒に取り組んだ成功事例について話しをすることで、応募先企業へあなたに関する良いコメントを提供してもらえる可能性も上がります。リファレンスとなってくれた人も多忙なため、どのようにコメントして欲しいかを伝えておくのも良いでしょう。
面接のお礼メールに返信が来たらどうする?
基本的にお礼メールに返信はないものと思って良いでしょう。仮に返信があった場合は、「返信をくれたことに対するお礼」「選考が進んだ際には頑張りたい」もしくは「働きたい思いがより強くなった」などの前向きな言葉を添えて返信します。
お礼メールへの返信例文
【宛先】 ○○会社 ○○課 △△様 【本文】 ○○(所属などを簡潔に)株式会社の□□です。 お忙しい中、ご返信をいただき誠にありがとうございます。 それでは、選考結果お待ちしております。 何卒よろしくお願い致します。 【氏名】 □□ □□ 【電話番号】○○-○○○-○○ 【メールアドレス】××@××.jp |
お礼メールは迅速に感謝の気持ちを込めて伝えよう
今回は、企業へのお礼メールの重要性と送る時のマナーをご紹介しました。お礼メールは、企業に対する熱意や感謝の気持ちを伝えたい時に送るものです。送るのであれば迅速に、「自分の言葉」を使って、お礼メールを送りましょう。
関連コンテンツ
すべて見る海外留学を通じて得られるスキルや経験は、キャリア形成にどのような影響を与えるのでしょうか? 今回は、ロバート・ウォルターズ・ジャパンで海外からの転職を支援しているAyako Shimizu(以下、Shimizu)と、EF(Education First)でセールス・ディレクターを務めるReina Araki(以下、Araki)さんが、海外経験を活かしたキャリア構築について語ります。 フル動画はページ下部でご覧いただけます。 インタビュー内容 Shimizu:皆さんこんにちは、ロバート・ウォルターズの清水です。本日は海外留学プログラムを提供しているEF社の荒木れいなさんに、「キャリアに活きる留学
もっと読むビジネス環境が急速に変化する中、キャリアも進化する必要があります。今は転職を考えていないかもしれませんが、あなたのスキルや経験を最大限に活かすチャンスを逃していませんか?転職は、キャリアアップや新しい刺激、柔軟な働き方を手に入れるための一つの道です。そして、忙しいビジネスパーソンでも、転職エージェントを活用することで効率的かつ戦略的にキャリアを進めることができます。 キャリアの未来を考えるとき、可能性を広げる選択肢の一つとして、ぜひ転職を視野に入れてみませんか? 現代のビジネス環境は急速に変化しています。テクノロジーの進化、グローバルな競争、リモートワークの普及など、多くの要因が企業と個人のキ
もっと読む海外から日本への帰国が決まったら、日本での新たな生活に向けて準備を進める必要があります。そんな引っ越しを控えている方のために、スムーズに準備を進めるためのタイムラインに沿った帰国ガイドをご用意しました。 帰国前の準備から帰国後の手続き、生活インフラの手配、ご家族がいる方に向けた幼稚園・保育園・学校探しや入学手続き、日本での仕事開始に向けた準備など、押さえておくべき要点をまとめています。 日本での新たな生活をスタートに向けて、さっそく準備を始めましょう。 ガイドへのアクセスはこちら *ロバート・ウォルターズでは海外から日本へ帰国して働くことを検討している方へキャリアサポートをしています。 海外か
もっと読む